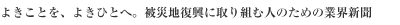より良いライフスタイルを提供する。
株式会社オノデラコーポレーション 前例となり、地域に選択肢をつくる

オノデラコーポレーション専務取締役の小野寺靖忠さん(左)
「少子高齢化が進む気仙沼。18歳で人口が流出する背景には、仕事場や遊び場における『選択肢の少なさ』がある」。その選択肢の一つとして「コーヒーショップと共にある生活」を提供する事で、ここに住みたいと思う人を増やしたいと考えた。またフランチャイズビジネス化することで、都会で働く人がオーナーとして田舎に帰る仕組みをつくれないかと試行錯誤を繰り返した。震災前には、ドライブスルーの店舗や大型書店内での出店など、テイクアウト主体の店を五店舗展開、港近くに焙煎工場を作るまでに成長していた。
震災では、このうちの二店舗と焙煎工場、製菓工場、事務所、自宅が津波に流され、焙煎前の生豆もすべて失った。再建にあたっては、知人からの紹介で出会ったクラウドファンディング「セキュリテ応援ファンド」の第一期の募集に参加した。「前例が無いことでも、誰かが始めて風穴を開けておけば、後に続く人が出る。被災地に一つの選択肢が増える。『田舎暮らしが豊かじゃない』とコーヒーショップを始めたのも一緒。選択肢があれば、何とかしようという人が出てくる」という気持ちだったという。

仮設店舗ではあるがコーヒーのある豊かなライフスタイル提供にこだわる
「『より良いライフスタイルを提供する』というのが一番の姿勢。復興、復旧後10年たった後も、そこに生き続けることを主眼に入れて、事業に取り組む必要がある」。そう考える小野寺さんは、気仙沼市の震災復興市民委員会に参画するなど街の復興にも積極的に取り組んでいる。その中で描かれている町の未来像には、「世界一の港町」として「おしゃれでかっこのいいまち」などが盛り込まれている。こうした町の復興と歩調を合わせつつ、資金が生きるタイミングを腰を据えて計っている状況だ。
共存共栄できるしくみをつくる。
一般社団法人三陸海産再生プロジェクト 市民ファンド手法による流通変革

プロジェクト支援先との 打ち合わせの様子
縁のあった東京の会社の支援を受けつつ、協賛する漁師を組織化。2011年5月に立ち上がったのが一般社団法人三陸海産再生プロジェクトだった。
このプロジェクトは、支援を希望する会員からの入会金を、漁業者が共同で利用できる加工設備や漁具の整備にあてる。そこで生産された加工品は、会員に対しては特別価格で提供されるというもの。支援者をそのまま顧客にする市民ファンド的な手法を用いて、海産物の流通を変えようという枠組みだ。

支援金で購入した定置網の網づくりをボランティと行う
自社の復興も見通せない状況の中、全く異なる事業に無償で取り組むことに対してさまざまな議論もあった。しかし、「水産業の現状を変えたい」という想いでプロジェクトを進める木村さんたちの姿に多くの人々が賛同し協力するようになったと言う。
漁師と加工業者が流通で協力し、製造で協力し、と徐々に協力関係が強化されるようになれば、水産業の構造自体が変わる。それは結果として自社のみならず業界全体の収益向上につながる。すべてが失われた今だからこそ、漁業者と加工業者、消費者が一体になって新しい仕組みをつくる必要がある。そんな哲学が、「復興」ではなく「再生」という言葉に込められている。
2013年春、新工場の完成に伴い、木村さんは本業の水産加工の復旧に専念するようになった。プロジェクトの代表理事と事務局体制はボランティアに委ねられたが、支援先の漁業者が直接東京の市場に営業する取り組みが始まるなど、新たな動きも生まれている。
ここで取り上げた四社に限らず、事例集に掲載されている企業の多くは、震災を期にビジネスモデルの大幅な変更や再構築(リストラクチャリング)、投資・経営計画の修正などを行っている。戦略的に考えるならば、被災地以外に移転し、新たな事業に取り組むという選択肢もあり得る。それをせずに現地再建にこだわるのは、「地域があってこそ自社がある」「自社は地域の担い手である」という強い意識があるからだ。
言い方を変えれば、地域の担い手としての役割を果たすことが経営の主題となっている。
その地で暮らし続けるという前提の下、長期にわたって必要とされていることが戦略の要となる。そして、それが求心力となり再建につながっていると言えるだろう。
(文/出藍社松崎光弘)
Tweet