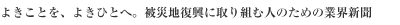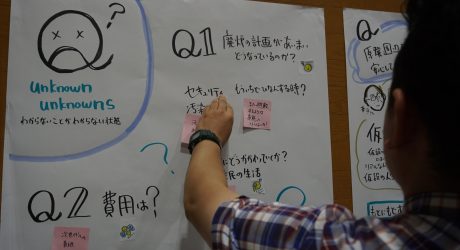農村資源×企業ニーズで事業化に成功

曽根原代表。活動の軌跡と未来へのビジョンは、自身の著書『日本の田舎は宝の山』にも詳しい。
代表の曽根原さんが活動を開始して18年。「企業ファーム」の提携先には三菱地所、博報堂など大手企業が名を連ね、交流人口は年間3000人以上。事業を通じて活用される農村の資源は、年一億円を超える。現在東北が向き合う大きな課題である、事業づくりへのヒントを得るべく、話を伺った。
コンサルティングから農業、地域おこしへ

三菱地所グループが開墾した「空土(そらつち)ファーム」の田植え風景。
95年、曽根原さんは北杜市の白州(はくしゅう)町に移住し、農業と林業を始めた。朝から晩まで夢中で働き、野菜の直売所やオーガニックレストランの運営、別荘オーナー向けの薪の販売、オリジナルの薪ストーブ製作などで、移住から5年後には年1000万円を売り上げるまでになった。01年にNPOを設立、メディアからの取材も増えた。すると町役場から声がかかった。「消滅寸前の増富(ますとみ)という限界集落を救ってくれないか」。
若者のボランティア、研修で地域を開墾

採れた酒米から昨年出荷した「純米酒丸の内」は4700本がほぼ完売に。
03年、行政と連携して構造改革特区の認定を得ると、曽根原さんは増富での活動を開始した。行ったのは、都会の若者による「開墾ボランティア」。インターネットと、顧客ネットワークを使って呼びかけた。当時は就職超氷河期で、ニート・フリーター・就職浪人が問題になった年。都会で活躍の場のない若者が年500人規模で集まった。空き家があるためボランティアの宿泊所には困らない。さらに、かつて町が補助金で建てた立派な温泉施設まで空いていた。地域には若者や外国人の笑顔が溢れるようになり、3年間で3ヘクタールの農地が復活した。
また同時に、農業者を育成する研修事業も開始した。これは地域に、特に若い世代の移住者を増やすためでもある。曽根原さんが期待したのは、農業の基礎能力をつけ、それを川下に繋げる技術を発揮できる人材。例えば都会でデザイナーをしていた人は、半農・半デザイナーという形で生業を立てながら地域に貢献できる。「えがおつなげて」では、移住までに必要な、体験や半移住などの段階を伴走しながらサポートしてきた。
曽根原さんは言う。「限界集落にボランティアを入れて開墾した。これはある意味、東北の復興と重なる部分があったかもしれません。ただ、被災地でも限界集落でも、若いボランティアにできることは、マイナスをゼロにすることまで。そこから、地域の経済を回していくことが、次のステップとして大事なんですね」。
Tweet