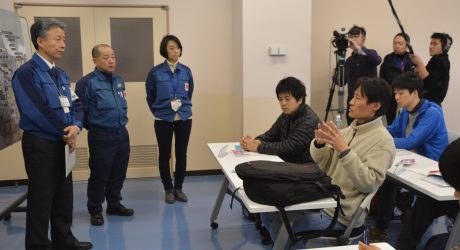どこに住んでも浪江町民
私たちにとっての等身大の「復興」ってどういうことなのだろうか。子どもたちの父親であり母親である若手職員との度重なる勉強会、町民の方々が多く集う検討委員会において、悩みに悩みつつ、議論が白熱しぶつかり合う中でたどり着いた先が、次の考えでした。
私たちにとって、まず大切にすべきなのは、「一人ひとりの暮らしの再生」なのではないかということ。今、町民全員が町を離れている。もしかしたら今後、一人ひとりがそれぞれの選択をし、近く、さらに遠くに離れるかもしれない不安を持っている。「町に残る人だけが町民」ではなく、震災前に暮らしていた私たち全員が町民と考えよう。もともと多様なバリエーションで暮らしていた一人ひとりの暮らしが、少しでも平和になっていくことを願いたい。町に戻ることが幸せと感じる方のためには、安心して帰って来れる環境を作ろう。一人ひとりがどちらも選んでも良い。そんな想いから復興ビジョンのサブタイトルとして「~どこに住んでも浪江町民~」の言葉が引き出されました。
「どこに住んでも浪江町民」は人がいてこその自治体にとって、非情な重さを持っています。よそに住むことを認めていくことは、ある意味自治体を否定するものでした。ただ、過酷な現実、そして一人ひとりの選択が一様ではないことの事実を踏まえていく中では、何より町民が第一、その考え方にならざるを得なかったのです。これは町民による委員会だからこそ導くことが許された基本方針だったのではないでしょうか。
その時の私たちには、そういう町民の選択のあり方自体を認めていくことが、町民の願いであり、そして町民の方々が互いに寄せ合う心あるメッセージなのではないかと思えました。それらの議論を理解した上で、原案を変えることなく採択した浪江町の馬場有町長、そして議会全員のメンバーにはその包容力の大きさに頭が下がるばかりです。これも住民に近い「自治体」だからこそ寄り添える力なのかもしれません。
対立を超えた「ふるさとの再生」に至る道程
もう一つ、厳しい議論だったのが「町」の復興でした。「そもそも帰れない」「いや帰れる」という「帰る、帰らない」という議論による分断。そして、帰れないならいわゆる「復興」は無用、お金をもらって町は捨てるべきとの論も根強くありました。マスコミでも、この議論がわかりやすかったせいか、注目を引きつけ、「町が割れている」、「帰りたい町役場」vs「帰りたくない町民」との構図で取り上げられたことも多くありました。それぞれの町民が傷つけ合う局面が生まれていました。
これは「見えない」「分からない」放射線への不安と、町全体の生業と暮らしが失われた中で直面する再生の難しさがあったとともに、それ以上に根深い問題がありました。それは「選択が許されない状態」。多くの対立の根はそこに潜んでいました。
避難指示の制度は、指示が続く間は帰れないが支援はする。一方、指示が解除されれば、帰れるが支援は打ち切るという意味あいがありました。「帰る」ことにより、帰りたくない人も帰らざるを得ない状況が生まれる。「帰らない」ことにより、帰りたい人も帰れなくなる。そうなると、相手の意見が通ることは、自分の存在を脅かすことになります。
気がつくと互いに支え合うべき仲間の間に対立が生まれ始めていきました。さらに、町はどちらを判断するのか。いくつかのマスコミはそこに注目しドラマを期待しました。ところが、現実は期待する内容よりも、遙かに深いものがありました。対立の先にあるもの、完全ではありませんが、多くの悩みを交わし合う中で、ようやくそこに迫ることになっていったのです。そこにたどり着くまでには、二つの出来事が大きな貢献を果たしました。
1万人を超える町民アンケート
一つは町民アンケートでした。多くの声を丁寧に聞きたい、そう考え、私たちのチームでは全「世帯」アンケートをやめることを決定しました。その上で敢えて困難を承知で、高校生以上の全「町民」アンケートの実施に踏み切りました。外部委託もできず、震災対応に追われる職員が直営で集計作業に当たるこという過度な負担を覚悟した上でのチャレンジでした。
その結果、18,000人中、11,000人という驚異的な回答率が生まれました。一つ一つのアンケート用紙を手に取ることで見えてきたこともありました。「帰る」「帰らない」の集計が全てと考えますが、実際はそうではありませんでした。しわくちゃになった回答用紙に残された、それぞれを何回も行ったり来たりした気配、欄外への「決められないのに」というメモ。帰ると答えつつ文末の自由意見の相反する悩み、その逆も当然ありました。パーセントの陰で見えなかったものが、はっきりと見えてきたのです。そこからは選択できる状態にない中で、選択を迫られる町民の複雑な心中がありました。
「ふるさとがどうなっても良い」とどの程度の方が思っているのか、そこもアンケートを工夫する中で、たどり着くことが出来ました。「帰らない」と答えた方、いわば「町を捨てた」と見なされかねない回答です。その上でその方たちに「町の復旧・復興は必要か」と尋ねました。そこから浮かびあがったのは、帰られないと思っている方の約8割弱は、それでもふるさとは良くなって欲しいという願いを持っていることでした。
他県に住まいを決めた町民の方が、交流の場で言葉を詰まらせていた風景が重なります。「自分はやむを得ずふるさとを捨てた。自分はふるさとに直接携わることはできなくなった。でも、自分のできることは精一杯していきたい」。たとえ自分の町に住まなくなったとしても、ふるさとはふるさととして、しっかりと存在し続けて欲しい。切なる訴えがそこにはありました。
止められない涙。子供たちが教えてくれたもの
もう1つ、強いインパクトを与えたのが、子どもアンケートでした。これも浪江町の若手スタッフの想いからスタートしたものでした。「果たして今の大人だけに聞けば済むのだろうか」「将来ふるさとを担う小中学生に全く意見を聞かなくて果たして良いのか」そんな疑問から、業務に追われる中にもかかわらず、実施に踏み切りました。そして、子どもたちの素直な思いを聞きたいとの趣旨から、集計やまとめが膨大となる、自由記載欄を中心としたアンケートに彼らは踏み込みました。
全員分のアンケートをまとめたものを、はじめて手にしたのはホテルのロビーでしたが、一つ一つの回答に目を通す中で、ほほに流れる涙を止めることができませんでした。一人一人の手書きの文字から見える、子どもたちの想いは、大人達の想像を超えています。「大人になったらどんな町になってほしいですか?」との問いに対して、都市部に避難している子どもたちなので、当然、東京のような都市になって欲しいとの声が大多数と考えていたのですが、真逆の結果が浮かびました。「元の町のような『賑やかな』町に戻って欲しい」「前のように『楽しい町』になって欲しい」「僕が大人になったら必ず町を取り戻します」。ページをめくってもめくっても、そんなふるさとに対する深くも熱い想いが、書き綴られていました。
なんと子どもたちは曇りのない眼で物事を見ているのだろう。今の大人、そしてかつての大人達が積み上げてきたふるさとが、子どもたちの目を通して見ていくとどれほど価値があるものだったのだろうか。私たち大人が見えない、積み重ねた町が持つ価値。このアンケートにはそういったヒントが数多く潜んでいました。私の原点の一つとなりました。
さらに、このアンケートは私個人だけでなく、町民の検討委員会、議会の議論にも強い影響を与えました。苦しくて放り出したくなる誘惑の中、大人達に向けられた子どもたちのまっすぐな想い。このアンケートに向き合った私たち大人として、何をすれば応えられるのだろう。そんなインパクトが生まれていました。
Tweet